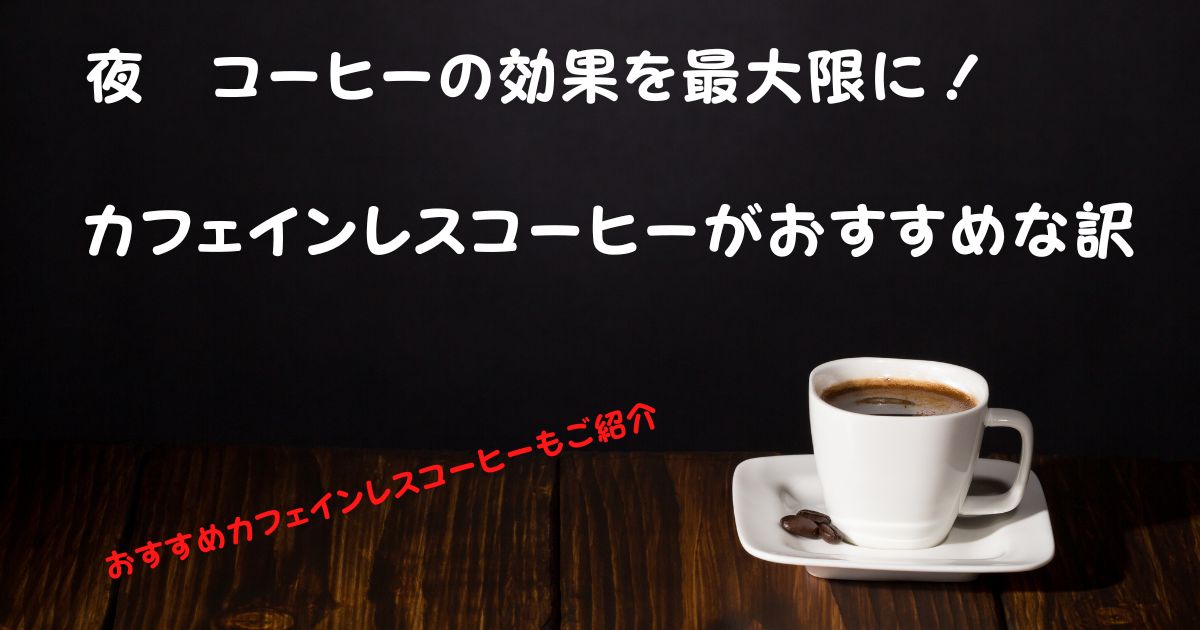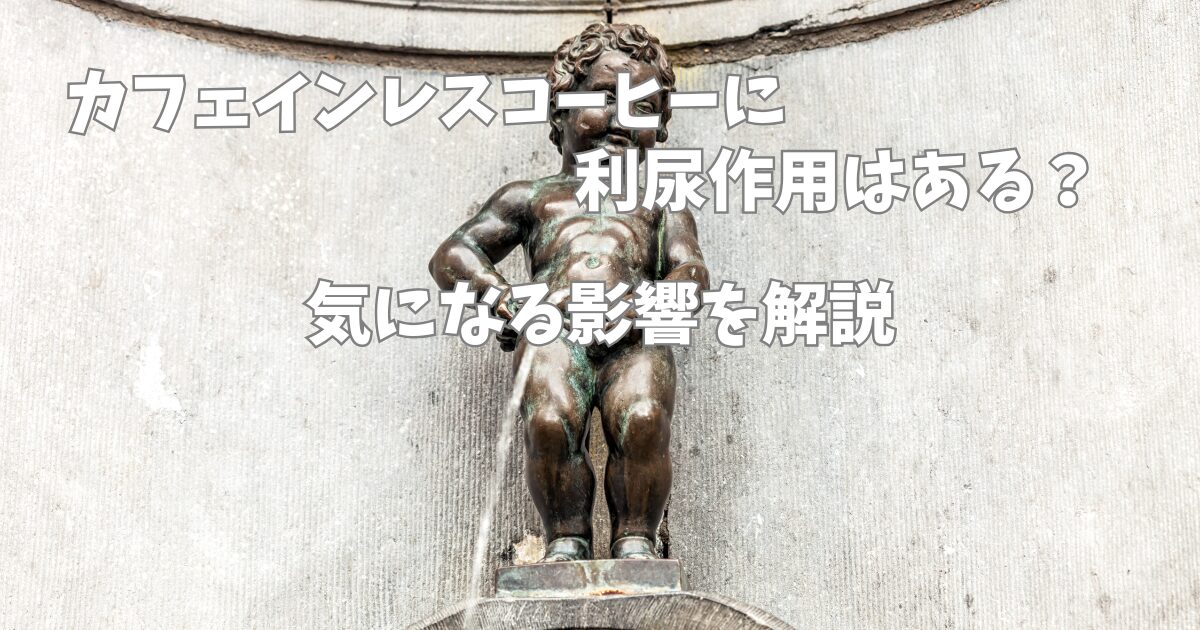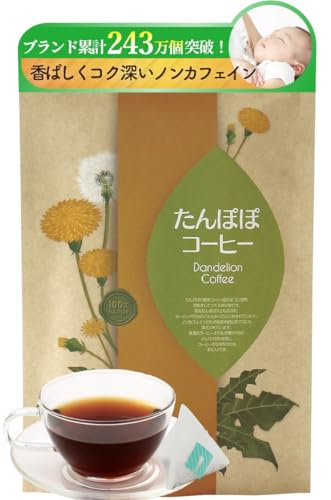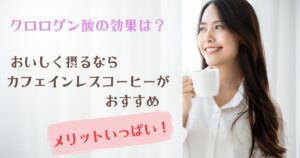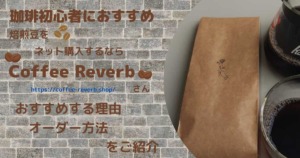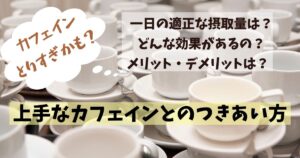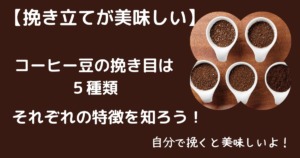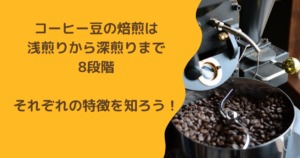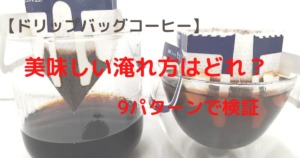カフェインを控えたい方に人気のカフェインレスコーヒーですが、実は「シュウ酸」の含有量についてはあまり知られていません。
シュウ酸とは、尿管結石の原因にもなる成分で、カフェインを除いたからといって減るものではありません。
本記事では、カフェインレスコーヒーのシュウ酸含有量を中心に、通常のコーヒーやお茶との比較、たんぽぽコーヒーなどの代替飲料、さらにはコーヒーの飲み方や工夫まで詳しく解説します。
コーヒーと健康を両立させたい方に向けて、知っておきたいポイントをわかりやすくまとめています。
- カフェインレスコーヒーにもシュウ酸が含まれていること
- シュウ酸とカフェインは無関係であること
- シュウ酸の吸収を抑える工夫ができること
- 尿管結石リスクを減らす飲み方や食べ合わせがあること
カフェインレスコーヒーのシュウ酸含有量は?

- カフェインレスコーヒーでもシュウ酸は含まれている?
- コーヒーとシュウ酸抜きの関係はあるのか
- 食品ごとのシュウ酸含有量一覧
- お茶のシュウ酸含有量と比較しよう
- コーヒーに加えるミルク類とシュウ酸の関係
カフェインレスコーヒーでもシュウ酸は含まれている?
カフェインレスコーヒーであっても、シュウ酸は含まれています。
カフェインが除去されたことと、シュウ酸の含有量には直接的な関係がないため、注意が必要です。
カフェインレスコーヒーは、通常のコーヒー豆からカフェインのみを取り除いたものです。
しかし、シュウ酸という成分は、カフェインとは異なる化学構造を持っており、カフェインを取り除く処理の過程では基本的に減少しません。
つまり、どれだけカフェインが少なくなっても、シュウ酸の量には影響しないのです。
具体的な数値で見ると、一般的なコーヒーには100gあたり33mg程度のシュウ酸が含まれています。
カフェインレスコーヒーも、同じくこの程度の含有量とされており、摂取量によっては尿路結石などのリスクを高める可能性があります。
特に、既に結石の既往がある方や、家族にそうした体質の方がいる場合は、シュウ酸の摂取量に気を配る必要があります。
一方で、すべての人がシュウ酸を神経質に避ける必要があるわけではありません。
バランスの良い食事や十分な水分補給、カルシウムとの同時摂取によって、シュウ酸の体内吸収はある程度抑えることができます。
コーヒーに牛乳を加えて飲むことが多い方は、自然と吸収リスクを減らしているとも言えるでしょう。
このように考えると、カフェインレスだからといって安心しすぎるのではなく、「カフェインは減ったがシュウ酸はそのまま」と理解しておくことが重要です。
健康のためにカフェインを控えている方は、同時にシュウ酸の摂取状況にも目を向けてみてください。
コーヒーとシュウ酸抜きの関係はあるのか
「シュウ酸抜きのコーヒー」は、現在のところ一般的には存在しません。
つまり、コーヒーとシュウ酸を切り離すことは難しく、基本的にはすべてのコーヒーに一定量のシュウ酸が含まれていると考えるべきです。
コーヒーに含まれるシュウ酸は、植物由来の自然成分であり、焙煎や抽出方法を変えても大きく減少することはありません。
カフェインを除去する「デカフェ処理」のように、シュウ酸を除去する専用のプロセスは現時点ではほとんど確立されていないため、「シュウ酸フリーのコーヒー」は市販されていないのが実情です。
ただし、シュウ酸の吸収を抑える方法はいくつか存在します。
例えば、コーヒーをブラックで飲むのではなく、ミルクやクリームを加えると、乳製品に含まれるカルシウムがシュウ酸と結合し、腸内で吸収されずに排出されやすくなります。
また、空腹時に飲むのではなく、食後に摂ることで、食事に含まれる栄養素と一緒に吸収されるため、シュウ酸の単独吸収が抑えられる可能性があります。
一方で、「シュウ酸が含まれているからコーヒーを一切飲まないほうがいい」とは言い切れません。
コーヒーには抗酸化作用やリラックス効果、集中力向上などのメリットもあるため、すべてを否定するのはもったいないことです。
大切なのは、体質や健康状態に応じた飲み方を選び、必要であれば量を調整するということです。
このように、現状では「コーヒーのシュウ酸だけを抜く」ことは困難ですが、飲み方を工夫することで影響を和らげることは可能です。
適切な知識を持ったうえで、コーヒーとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
食品ごとのシュウ酸含有量一覧

日常的に口にする食品の中には、意外にもシュウ酸を多く含むものがあります。
特に尿路結石のリスクを考慮している方にとって、どの食品にどれくらい含まれているのかを知ることは、予防の第一歩となります。
まず代表的なのがほうれん草です。
シュウ酸含有量は非常に高く、生の状態で100gあたり約0.7g(700mg)程度とされています。
他にも、ココアやピーナッツ、さつまいも、ナス、ブロッコリー、レタスなど、一般的に健康に良いとされている野菜や食品にもシュウ酸は含まれています。
具体的な一覧で見てみましょう。
| 食品名 | シュウ酸含有量(mg/100g) |
|---|---|
| ほうれん草(生) | 770 |
| 純ココアパウダー | 700 |
| バナナ(未熟) | 500 |
| レタス | 330 |
| さつまいも | 240 |
| ブロッコリー | 190 |
| ナス | 190 |
| ピーナッツ | 187 |
| パセリ | 170 |
| チョコレート | 117 |
このように、普段の食卓に登場しやすい食材でも、油断すると過剰なシュウ酸摂取になりかねません。
特に、健康意識が高く野菜を積極的に摂る人ほど、知らず知らずのうちにシュウ酸も多く摂取していることがあります。
ただし、シュウ酸を完全に避けることは現実的ではありません。
そこで重要なのが「食べ合わせ」や「調理法」の工夫です。
カルシウムを多く含む食品と一緒に食べることで、シュウ酸の吸収を抑えることができます。
例えば、ほうれん草をゆでてカルシウムを含むチーズと合わせる、ピーナッツを牛乳と一緒に摂るなど、ちょっとした工夫でリスクを減らすことが可能です。
このように、食品のシュウ酸含有量を知っておくことで、より健康的な食生活を構築できます。
単に「避ける」のではなく、うまく「付き合う」ことが大切です。
お茶のシュウ酸含有量と比較しよう

飲み物の中でも、日常的に摂取されやすいのがお茶です。
しかし、このお茶にもシュウ酸が含まれていることをご存じでしょうか。
特に紅茶や緑茶などの茶葉を使用した飲み物には、比較的多くのシュウ酸が含まれています。
代表的なお茶のシュウ酸含有量を紹介すると、紅茶は100gあたり約72mg、緑茶は約60mgとされています。
一見すると食材と比べて少ないように思えるかもしれませんが、飲み物は一度に大量に摂取しがちであるため、結果的にシュウ酸の摂取量が増えてしまうこともあります。
お茶と他の飲料を比べると、コーヒーは33mg/100gとされており、シュウ酸量はお茶に比べてやや少なめです。
一方で、ココアは100gあたり600mgを超えるため、明らかに高リスク飲料といえます。
ここからもわかるように、「お茶は身体に良いから安心」と思っていても、摂り過ぎれば必ずしも安全とは限らないのです。
ただ、すべてのお茶に気を使わなければいけないわけではありません。
例えば、麦茶やルイボスティー、ハーブティーの中にはシュウ酸含有量が非常に少ないものもあります。
これらは、シュウ酸を気にしている人にとって優秀な代替飲料といえるでしょう。
飲むタイミングにも注意が必要です。
空腹時や単独でお茶を大量に飲むと、シュウ酸が体内に吸収されやすくなります。
反対に、食事と一緒に飲むことで、食物中のカルシウムがシュウ酸と結びつき、吸収されずに体外へ排出されやすくなります。
このように、お茶の種類や飲み方によって、シュウ酸の影響は大きく変わってきます。
自分の健康状態に合わせて、お茶の種類を見直してみるのもひとつの手です。
適切な選択ができれば、お茶も安心して楽しむことができるでしょう。
コーヒーに加えるミルク類とシュウ酸の関係

コーヒーにミルクやクリーミングパウダーを加えることで、シュウ酸の体内吸収を抑える効果が期待できます。
これは、ミルク類に含まれるカルシウムが、シュウ酸と結合して不溶性の物質となり、腸で吸収されずに便として排出されやすくなるためです。
そもそもシュウ酸とは、野菜や飲料などに含まれる天然成分の一つで、体内でカルシウムと結びつくと結晶化し、尿管結石の原因になることがあります。
コーヒーはそのシュウ酸を含む代表的な飲み物の一つです。
ブラックで飲むと、摂取したシュウ酸がそのまま体内に吸収されやすくなるため、コーヒーの飲み方によって健康リスクが変わってくるのです。
ここで注目されるのが、牛乳や豆乳、クリープやコーヒーフレッシュといった添加物です。
特に牛乳はカルシウムを豊富に含んでおり、シュウ酸と結合するには非常に適した食品といえます。
朝食と一緒にカフェオレにする、もしくは小さじ1〜2杯程度のミルクを加えて飲むだけでも、シュウ酸の体内吸収を抑えるサポートになります。
一方で、コーヒーフレッシュやクリープは、カルシウムの含有量が製品によって大きく異なります。
植物性油脂をベースにした製品では、カルシウムはあまり含まれていない場合もあり、あくまで「味やコクを加える目的」で作られているため、シュウ酸対策という観点では十分とはいえません。
カルシウム摂取を意識する場合は、成分表示を確認することが重要です。
また、牛乳アレルギーや乳糖不耐症の人にとっては、無理に乳製品を摂ることが難しい場合もあります。
その場合は、カルシウムを強化した植物性ミルク(例:カルシウム添加の豆乳やアーモンドミルク)を活用するという選択肢もあります。
このように、コーヒーに何を加えるかによって、シュウ酸の体内への影響をコントロールすることが可能です。
ブラックで飲むのが好きな人も、体調やリスクに応じて、ミルクを取り入れる工夫を試してみる価値はあるでしょう。
ほんの少しの工夫で、健康へのリスクを軽減できる飲み方を選ぶことができます。
参考文献:原泌尿器科病院「尿路結石の再発を防ぐ食事について」
カフェインレスコーヒーのシュウ酸含有量と飲み方の工夫

- 尿管結石とコーヒーは何杯までなら安全か
- たんぽぽコーヒーのシュウ酸はどうなのか
- カルシウムと一緒に摂ることでリスクを下げる
- 利尿作用との付き合い方に注意
- 食後に飲むなど日常でできる工夫
- シュウ酸を気にする人への飲み方アドバイス
尿管結石とコーヒーは何杯までなら安全か
コーヒーの摂取量と尿管結石のリスクには一定の関係があると考えられていますが、「何杯までなら確実に安全」といった明確な基準はありません。
ただし、目安としては1日2〜3杯程度までにとどめるのが無難とされています。
コーヒーには利尿作用があり、適量であれば尿の排出を促すことによって、体内の老廃物やミネラルが過剰に蓄積するのを防ぐ働きもあります。
しかしその一方で、コーヒーに含まれるシュウ酸は、尿管結石の主な原因物質の一つです。
特に「シュウ酸カルシウム結石」は、全体の約8割を占めるとされており、コーヒーを含むシュウ酸の多い飲食物を過剰に摂取することは、リスクを高める要因になります。
一杯のコーヒーに含まれるシュウ酸の量は約30〜40mg程度とされており、それ自体が極端に多いわけではありません。
ただ、毎日何杯も飲み続けることで、シュウ酸の総摂取量が増えていきます。
また、水分補給の目的でコーヒーばかり飲んでいると、逆に体内の水分バランスが崩れ、尿が濃縮されて結石が形成されやすくなるおそれもあります。
このため、コーヒーを飲む際は、ブラックで飲むよりもミルクを加えるなど、シュウ酸の吸収を抑える工夫が効果的です。
さらに、コーヒーだけに偏らず、水やお茶などシュウ酸の少ない飲み物も積極的に取り入れるとよいでしょう。
結石の既往歴がある方や、家族に結石の経験者がいる場合は、なおさら慎重な摂取が求められます。
コーヒー自体を禁止する必要はありませんが、「習慣的に飲むもの」だからこそ、日々の量と飲み方を意識することが大切です。
たんぽぽコーヒーのシュウ酸はどうなのか

たんぽぽコーヒーは、一般的なコーヒー豆を使用せず、たんぽぽの根を焙煎して作られるノンカフェイン飲料です。
このため、カフェイン摂取を避けたい人にとっては優れた代替品ですが、シュウ酸の含有量に関しては注意が必要です。
一般に、たんぽぽの葉や根にはシュウ酸が含まれており、量としては生のたんぽぽ全体で100gあたり0.2〜0.3g(200〜300mg)前後とされています。
これはほうれん草ほどではないにせよ、コーヒーと比較しても決して低い数値とは言えません。
特に、たんぽぽコーヒーのように濃縮された形で摂取する場合、シュウ酸の影響が無視できないレベルになる可能性があります。
たんぽぽコーヒーは健康食品としても人気がありますが、「体に良さそう」というイメージだけで大量に飲むのは避けたいところです。
たんぽぽの根には利尿作用やホルモンバランスの調整に役立つ成分が含まれているとされる一方で、シュウ酸を過剰に摂取すれば結石リスクを高めることもあるからです。
とはいえ、1日に1〜2杯程度のたんぽぽコーヒーを楽しむ分には、大きな問題になる可能性は低いと考えられます。
飲みすぎにさえ注意すれば、カフェインレスの選択肢として優れた特性を持っています。
また、カルシウムと一緒に摂ることや、食後に飲むことでシュウ酸の吸収を抑える工夫も取り入れると、より安心して楽しむことができるでしょう。
つまり、たんぽぽコーヒーも「カフェインがないから安全」と単純に考えるのではなく、シュウ酸を含む植物飲料であることを理解し、適量を守って取り入れることが賢明です。
どんな食品や飲み物でも、健康効果を引き出すには、正しい知識とバランスの良い取り方が重要です。
カルシウムと一緒に摂ることでリスクを下げる

シュウ酸の健康リスクを抑えるためには、カルシウムとの同時摂取が非常に有効です。
なぜなら、カルシウムは腸内でシュウ酸と結合し、不溶性の塩として体外へ排出されるため、吸収されにくくなるからです。
この作用によって、尿中に排出されるシュウ酸の量が減り、結果的に尿管結石の予防につながります。
たとえば、シュウ酸の多いほうれん草やコーヒーを摂る際に、牛乳やチーズ、ヨーグルトといったカルシウムを含む食品を一緒に摂ることで、腸内でのシュウ酸吸収を抑制する効果が期待できます。
コーヒーに牛乳を加えてカフェオレにしたり、サラダにチーズをトッピングするだけでも十分です。
このような「組み合わせ」を意識することで、日常的な食事の中でも自然にリスクを減らすことができます。
また、カルシウムは食品から摂るのが基本ですが、食事だけで足りない場合はサプリメントを使う方法もあります。
ただし、サプリで摂る場合には、摂取のタイミングが重要です。食事と一緒に飲むようにしないと、体内で余剰になったカルシウムが尿中に排出され、かえって結石のリスクが高まる可能性もあります。
したがって、カルシウムはあくまでも「食事と一緒に摂る」ことがポイントです。
このように、シュウ酸を過剰に摂取しがちな現代の食生活においては、カルシウムとのバランスが健康維持のカギを握っています。
シュウ酸を完全に避けるのは現実的ではありませんが、カルシウムとの適切な摂り方を知ることで、そのリスクを大きく軽減することが可能です。
意識して実践することで、日々の食事がより安全で健康的なものになります。
利尿作用との付き合い方に注意

コーヒーやカフェインを含む飲料には、一般的に利尿作用があることが知られています。
利尿作用とは、腎臓の働きを促進して尿の量を増やす効果のことで、一見すると体内の老廃物を排出する良い効果のように思われるかもしれません。
しかし、過剰に働いた場合には体内の水分バランスが崩れ、結果として脱水を招いたり、尿が濃くなって結石のリスクを高めることもあるのです。
特に注意したいのが、「水分を摂っているつもりが、実際には体から多くの水分が排出されてしまっている」という点です。
たとえば、コーヒーを頻繁に飲んでいると、飲んだ量以上に尿が出てしまい、体内が軽い脱水状態になることがあります。
この状態が続くと、尿中のシュウ酸やカルシウム濃度が高まり、結石が形成されやすくなるのです。
そのため、利尿作用のある飲み物を摂るときは、それ以上の水分を別に補給することが大切です。
コーヒーを飲んだ後にコップ1杯の水を飲む、または日常的にこまめに水やお茶などで水分補給を心がけると、体内の水分バランスが保たれやすくなります。
特に運動後や暑い日には、より一層の注意が必要です。
さらに、就寝前や空腹時のコーヒー摂取も見直したいポイントです。
空腹時に利尿作用が強く働くと、水分や電解質のバランスが乱れやすくなります。
寝ている間は水分を補給できないため、夜間に脱水が進み、朝起きたときに尿が濃くなっているというケースも少なくありません。
このように、コーヒーやカフェインを含む飲料と上手につきあうには、ただ「量を減らす」のではなく、水分補給とのバランスや飲むタイミングを工夫することが重要です。
利尿作用そのものを悪と捉えるのではなく、体の反応を理解したうえで、日常の中で無理なく調整していくことが理想的なアプローチといえるでしょう。
カフェインレスコーヒーの利尿作用について、「カフェインレスコーヒーに利尿作用はある?気になる影響を解説」で詳しく取り上げています。合わせてご覧ください。
食後に飲むなど日常でできる工夫
カフェインレスコーヒーや通常のコーヒーを楽しみながら、シュウ酸の影響を抑えるためには、日々の飲み方に小さな工夫を取り入れることが大切です。
その中でも、「食後に飲む」というタイミングの選び方は、非常に有効な方法の一つです。
シュウ酸は体内に吸収されると、尿中でカルシウムと結びついて結晶化し、尿路結石の原因になることがあります。
しかし、食後であれば、食事に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラルと一緒に腸内で結合し、不溶性の形となって体外に排出されやすくなります。
このしくみを活用することで、シュウ酸が体内に吸収される量を抑えることができるのです。
たとえば、コーヒーを飲む習慣がある方は、空腹時を避けて食後に飲むよう意識するだけでも、体への負担を軽減できます。
また、コーヒーに牛乳や豆乳を加えると、飲み物の中にもカルシウムが補われるため、相乗効果が期待できます。
これなら特別な準備や制限をすることなく、自然な流れで実践できるはずです。
加えて、水分補給のタイミングも工夫するとより効果的です。
コーヒーは利尿作用があるため、飲んだ後にコップ1杯の水を追加で飲むようにすると、尿が濃縮されるのを防げます。
結果として、尿中におけるシュウ酸やカルシウムの濃度が薄まり、結石のリスクを下げることができます。
こうした日常の中でできるちょっとした工夫は、継続することで大きな差につながります。
何かを我慢するのではなく、「飲むタイミング」や「組み合わせ」に意識を向けること。
それが健康的にコーヒーを楽しみ続けるための鍵になると言えるでしょう。
シュウ酸を気にする人への飲み方アドバイス

シュウ酸の摂取を気にする方がコーヒーを飲む際には、いくつかの具体的なポイントを意識することで、健康への影響を最小限に抑えることが可能です。
これはカフェインレスコーヒーにも当てはまるため、「カフェインが少ないから安心」と思い込まず、シュウ酸という成分にも注目して飲み方を工夫する必要があります。
まず、「一度に大量に飲まない」というのが基本的なルールです。
たとえ1杯のシュウ酸含有量がそれほど多くなくても、毎日何杯も飲んでいれば、累積的に摂取量は増えます。
1日2〜3杯までにとどめ、間隔をあけて飲むようにすると、体への負担も少なくなります。
次に意識したいのが、「カルシウムと一緒に摂る」という工夫です。
前述の通り、カルシウムは腸内でシュウ酸と結びつき、体外への排出を促す働きがあります。
牛乳やチーズ、ヨーグルトなどを一緒に摂ることが理想的ですが、コーヒーにミルクを加えるだけでも効果は期待できます。
また、「代替飲料の活用」も選択肢の一つです。
コーヒーの代わりに、麦茶やルイボスティー、ハーブティーなど、シュウ酸の含有量が少ない飲み物を取り入れることで、日常の飲み物からのシュウ酸摂取を減らすことができます。
全てを我慢するのではなく、バリエーションを持たせることが継続のポイントです。
さらに、「空腹時の摂取を避ける」ことも大切です。
空腹状態ではシュウ酸がより吸収されやすくなります。
したがって、コーヒーを飲むタイミングは、軽食や食事の後にするのが安全です。
最後にもう一つ加えるなら、「水分をこまめに摂ること」も忘れてはいけません。
コーヒーを飲むことで利尿作用が働くと体内の水分が失われがちになりますが、それを補うように意識して水を飲むことで、尿が薄まり、結石ができにくい状態を保てます。
これらのポイントを日常的に意識すれば、シュウ酸を気にする方でも安心してコーヒーを楽しむことができます。
大切なのは、無理に制限するのではなく、身体に優しい飲み方を「選ぶ」意識を持つことです。
カフェインレスコーヒーのシュウ酸含有量を正しく理解し活用するために

カフェインレスコーヒーは健康的な選択肢として注目されていますが、シュウ酸の存在についても正しく知っておくことが重要です。
以下に、知っておきたいポイントを整理しました。
- カフェインレスでもシュウ酸は含まれている
- カフェイン除去とシュウ酸除去は無関係
- 一般的なコーヒーと同等のシュウ酸量がある
- シュウ酸は焙煎や抽出では大きく減らない
- シュウ酸フリーのコーヒーは市販されていない
- ブラックよりミルク入りのほうが吸収抑制に有効
- 食後に飲むと吸収されにくくなる
- コーヒー1日2〜3杯までがリスクを抑える目安
- 利尿作用により水分不足が結石リスクを高める
- コーヒーの代替にたんぽぽコーヒーも選択肢
- たんぽぽコーヒーもシュウ酸を含むため注意が必要
- カルシウムと一緒に摂ると吸収が抑えられる
- お茶類の中にはシュウ酸の多い種類もある
- 麦茶やルイボスティーは低シュウ酸で安心
- 水分補給と組み合わせることでリスクをさらに軽減できる
カフェインレスだからといって安心しきらず、シュウ酸への理解と飲み方の工夫を取り入れることで、より健やかな日常につながります。
当サイト一押しのインスタントカフェインレスコーヒーはこちら!